フィクションにおけるリアリティとは、そもそも物語を構成するための要素の一つにすぎない、というはやはり言い過ぎかもしれません。
しかし、一般小説よりも現実離れした小説の多いライトノベルにおいて、リアリティが最重要視すべき問題かと言われれば、やはり少し違う気もします。
では、そういったライトノベルにおいてリアリティが重要視される機会があるとすれば、それはやはり物語に奉仕するため、ということになると思います。
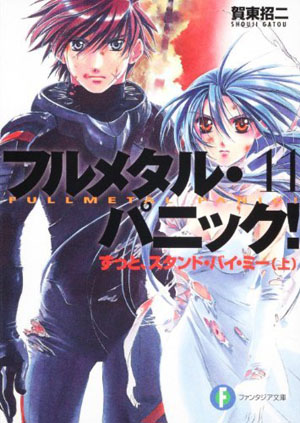
(図1)
長年続いた『フルメタル・パニック』シリーズ(図1)もついに完結を迎えていますが、この作品ではあからさまに荒唐無稽なテクノロジー、というのはほとんど存在せず、あくまで現実世界の現代の延長線上に存在するかのような世界として作中世界が造られていました。(実際は延長線上ではなく××レルワー××だったわけですが)。
この作品におけるリアリティとは、現実と極めて近い『日本』を描写することで、主人公・相良宗介がいかに現代日本(のようなの物語世界)の常識からずれた存在であるかを説明するための一種の装置でもありました。
物語が進みシルアス度が増すにつれ、宗介の非常識さがなりをひそめるとともに、物語のリアリティにも一部意味がなくなり始めた、いいかえると一種の荒唐無稽さ(パラ×××ールド設定など)が出てきた、というのは珍しい傾向のように思います。
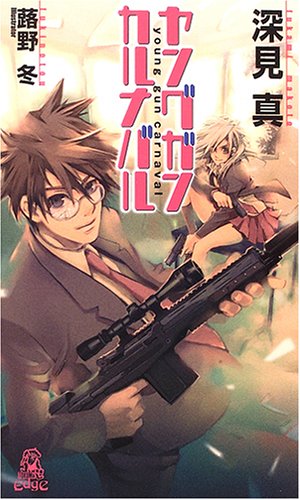
(図2)

(図3)
ライトノベルにおいて、現実世界(に似た物語世界…いいかげんしつこいですかね)を描く作家の代表として、深見真先生がいます。
「ヤングガン・カルナバル」(図2)に代表されるように、主人公は少年少女でありながら、ファンタジーではなく現実世界において、剣や魔法ではなく、銃や格闘技といった、現実世界にも存在する”暴力(バイオレンス)”を使って表現することの多い作風です。
また、今年文庫化された非ライトノベル作品「ゴルゴダ」(図3)では、妻子を殺された自衛官の男が、犯人たちに恐るべき復讐を遂げていき、やがて社会全体を巻き込む事件に発展していくさまを描いています。正直に言うと、主人公が事件を起こしていく過程は、ここまでうまくいくものか、というほど大きな事態に発展していくのですが、読んでいてさほど不自然に思わないのは、作中に表現されているリアリティが、読み手にプロットの荒唐無稽さを感じさせないための手助けになっているからだと思います。いわば、深見先生がライトノベルでのリアリティの使い方を一般小説に流用したのが「ゴルゴダ」の根幹だと(勝手に)思います。
ライトノベルのリアリティの話はいったん終了します。次回は(掲載されれば)50回目ということで、ずっと書きたかったあることを書き始めてみたいと思います。
(担当 有冨)



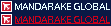
 このページの先頭へ
このページの先頭へ