最近「スレイヤーズ」のイラストレーター(専属、といって差し支えないかもしれません)あらいずみるい先生
の絵柄がまた変わったようです。(図1)

(図1:どうでもいいけど、ちょっと気になる絵柄変貌の巻)
あらいずみ先生の絵柄はけっこう変わっているので、それ自体は珍しいことでもないのですが、
上記の最新刊のイラストを見ると、どんどんナーガが「普通のキレイなお姉さん」化しているのは気のせいでしょうか。
ただでさえ、ナーガが作中で普段の「悪の女魔術師」以外の服を着ている時のイラストは生き生きしているのですが。
思いっきり話がそれました。本題は「ひぐらしのなく頃に」(図2)です。

(図2:本題です)
「ひぐらし」のヒットの度合というのは、ニンテンドーDSという、最も売れているゲームハードの一つで移植され発売されたことが一番の証明だと思います。
「ひぐらし」は、ゲームであること自体を逆手にとったような構成でした。
コンシューマではない、いわゆる同人ソフト版の「ひぐらし」には、アドベンチャーゲームには必須ともいうべき”選択肢”が全く存在しません。それが、逆説的にひぐらしのゲーム性を高めていった要因でもあります。
(以下ネタバレです)
「ひぐらし」は、同じ舞台設定の中で何度も時間を繰り返し、そのたびに違う事件を体験することで、プレイヤーおよび作中人物たちが事件の真相に近づいていくという構図をとっています。
つまり、一般的なゲームプレイヤーにとっては常識でもある「アドベンチャーゲームは何度も繰り返しプレイしていろいろなエンディングを見るゲームである」という設定を逆手にとって、
プレイヤーは全く選択肢などで物語を動かすことができないかわりに、さまざまなシナリオをプレイすることで、ゲームの全体像を把握できる、というのが「ひぐらし」の基本設定でした。
つまり、一般的なゲームプレイヤーにとっては常識でもある「アドベンチャーゲームは何度も繰り返しプレイしていろいろなエンディングを見るゲームである」という設定を逆手にとって、
プレイヤーは全く選択肢などで物語を動かすことができないかわりに、さまざまなシナリオをプレイすることで、ゲームの全体像を把握できる、というのが「ひぐらし」の基本設定でした。
(以上ネタバレ終わりです)
「ひぐらし」は、ゲームであると同時にノベルでもあるという、ある意味同人ソフトだからこそ成立しえたような作品でした。
その証拠に、PS2・DSに移植された「ひぐらし」には全て選択肢が追加されています。
その後、同人ソフトなどにおいてもノベルゲームは多様化していくのですが、ライトノベルにも大きな影響を与えつつあります。
…やっと本題に入れました。
「ひぐらし」の文章スタイルは、ある種「同人ソフト」という形態だからこそ許された、ともいえるような文体・技法を使っています。
乱暴に言うなら”やりたい放題”ともいえる自由なスタイルをとって書かれています。
ここ最近では、舞城王太郎作品(図3)の文体が一時期新しい、とされていたこともありましたが、ごく最近のライトノベルでは、
会話の多用(今までも一般小説より十分多かったのですが、さらに)、地の文の中立性の無さ、一人称の転換など、
これまでライトノベルでもそれほど多く見られなかったスタイルがまま見られるようになりました。
この現象が、今後ライトノベルをどのように導くのか、なかなか興味深いと思います。

(図3)
今回は以上になります。
次回のネタは、古いラノベを中心に。
(担当 有冨)
※この記事は2008/10/22に掲載したものです。


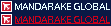
 このページの先頭へ
このページの先頭へ