
(図1 有川先生集めてみました)
有川浩先生が、現在小説界でかなり注目されている作家であることは、疑いようのないことです。
その読みやすい文章と多彩な恋愛風味や通り一辺倒でない人間賛歌と、なによりもその順調な刊行ペース(ここ大事)が読者に支持を受けているように思います。
代表作「図書館戦争」(図1:右端)はアニメ化もされました。

(図2 左/文庫版、右/ハードカバー版)
その有川先生のデビューは、前回も触れましたが電撃文庫「塩の街」(図2)です。
電撃大賞にて金賞を受賞し、見事デビューを果たしました。
担当は最初に読んだときに、その終末的な世界観と純粋なヒロインの対比が非常に良くできていて本当に面白かったのを覚えています。
その後新作を楽しみにしていたもののなかなか刊行されず、どうしたのだろうと思っていたら、その後出た第二作「空の中」は当時メディアワークスでは珍しかったハードカバーでの刊行で、当時驚いたものです。
その後も「海の底」「図書館戦争」など、作品はすべてハードカバーで刊行がされています。
そして、「図書館戦争」シリーズ終了後の作品は、文藝春秋・幻冬舎など、ライトノベルとはかなり遠い出版社からも発売されています。
有川先生の作家としての志向が、いわゆるライトノベルではなく『恋愛小説』要素の強い作品であったであろうことは、現在までの作品の傾向からいっても明らかです。
そして、そのことは2007年に刊行された「塩の街」のハードカバー版にて、完全に読者にも強く発せられる形になりました。
担当は文庫版の「塩の街」は傑作だと思います。そしてハードカバー版の「塩の街」も面白い内容でした。
しかし、ハードカバー版を読むと、そこにはある種の意思が感じられます。それは”ライトノベル”的なものとの決別です。ハードカバー版では、文庫版とは少しずつ設定が違うのですが、何よりもいわゆる活劇的なカタルシスが排除されてます。
象徴的なのが、追加された番外編のうち一つに、やや自己中心的な少年が登場し、主人公たちにかかわってくる一編です。きわめて陳腐な見方をすれば、これが年少の読者との距離感でもあるという観察も可能かと思います。
なによりも、ハードカバー版のあとがきでは、「塩の街」は本当は最初からハードカバーで出したかったが、賞をとってしまったので文庫で出さざるを得なかった、という内容のことが語られています。
つまり、結果はどうであれ、デビュー直前から有川先生(と編集サイド)には、一般的な意味のライトノベルへの志向はほとんど存在していなかったことになります。
有川先生は現在でも「ライトノベル作家」であること自身では口にされていますが、おそらく世間でそういう受け止め方をしている人は少ないでしょう。少なくとも、書店で有川先生の本が平積みになっているところから購入する客層からは、ライトノベル的な客層はもはや想像できません。
ここに、文庫とハードカバーの本にある、形容しがたいなにかを思わず感じてしまうのは、担当だけなのでしょうか。
書いているうちに何だか無意味にもやもやしてきたので、次回のはもう少し整理してこの話の続きです。
(担当 有冨)



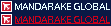
 このページの先頭へ
このページの先頭へ